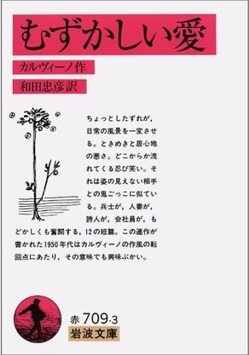最近、試写で『ローマ環状線、めぐりゆく人生たち』というイタリアのドキュメンタリー映画を見た。ローマを取り巻く高速道路GRAの周辺に住む、ひと癖もふた癖もある個性的な人物たちを定点観測のようにスケッチした愛すべき小品で、ヴェネチア国際映画祭金獅子賞を受賞しているが、プレスを読んで驚いた。監督のジャンフランコ・ロージが、「この映画はイタロ・カルヴィーノの『見えない都市』にインスパイアされた」と語っていたからだ。
イタロ・カルヴィーノは、多分、翻訳された作品をほとんど読んでいる唯一の作家といっていいかもしれない。亡くなって三十年近くの歳月が流れたが、彼の発見者であるチェーザレ・パヴェーゼと同様、未だに岩波文庫で陸続とその作品が復刊されているのはうれしい限りである。一時期、高橋源一郎が激賞したせいもあってか、カルヴィーノは、〈エレガントな前衛〉〈ポストモダンの作家〉などと称されて、実験的なメタ・フィクションの作家と目されがちだが、私にとっては、カルヴィーノとは、なによりも豊潤なイタリア映画の名作と同じように、〈美しい物語〉の語り手である。
最初に読んだのは、一九七一年に晶文社から刊行が始まった〈文学のおくりもの〉シリーズの『まっぷたつの子爵』 だった。その詩的で奇想に満ちた面白さにめまいのような感動を覚え、すぐさま『木のぼり男爵』(白水社)、『不在の騎士』(学芸書林)、『マルコヴァルドさんの四季』(岩波少年文庫)と読み継いで、すっかり魅了されてしまった。
とりわけ、十八世紀の啓蒙思想の時代を背景に、ある日、森の木に登って、一生涯、木から降りてこなくなった少年を描いた『木のぼり男爵』は、あまりの童話的な残酷さと澄み切ったユーモアの混交に圧倒された。
ちょうど、その頃、封切られた『フェリーニのアマルコルド』(73)に、主人公の少年が精神病院に入院しているテオ叔父さんを連れ出して、一家で郊外にピクニックにでかけるエピソードがあった。テオ叔父さんは、突然、田舎家のはずれにある樹にのぼりはじめる。そして、夕暮れになっても、降りて来ず、地平線の彼方に向かって、「女を抱かせろ!」と叫び続けるのだ。この涙が出るほど、可笑しい場面を見ながら、私は、まるで『木のぼり男爵』のようだ、と呟いた。
それ以来、ずっと長い間、私は、イタロ・カルヴィーノの魔術的な想像力とフェリーニのノスタルジアに満ちたサーカス的な夢想の世界は、きわめて近しいのではないかと思っていた。
一九八五年、不思議な偶然だが、カルヴィーノが亡くなる直前、雑誌『ユリイカ』が「イタロ・カルヴィーノ 不思議な国の不思議な作家」という特集を組んだことがあった。その号はとても充実した内容で、今も私の手元にあるが、とくにパゾリーニへの深い友情を感じさせる「パゾリーニへの最後の手紙」、偉大なコメディアン、グルーチョ・マルクスを追悼した「グルーチョの葉巻」などを読むと、カルヴィーノがいかに映画に深く傾倒していたのかが了解されるのだ。
カルヴィーノの没後、ずいぶん経ってから、『サン・ジョヴァンニの道――書かれなかった[自伝]』(朝日新聞社)が刊行された。この中にある「ある観客の自伝」という章は、カルヴィーノの幼少期から青春時代に出会ったアメリカ映画やイタリア映画への想いを綴ったメモワールで、とくに後半は、まるごとフェリーニへの熱いオマージュとなっている。たとえば、次のような一節はどうだろうか。
「フェリーニのヒーローの伝記――それを監督は毎回最初から撮りなおす――は、この意味でわたしのものよりはるかに典型的だ。若者が地方を離れ、ローマに出て、スクリーンの向こう側へ移って映画をつくり、自分自身が映画になるからだ。フェリーニの作品は、裏返された映画なのだ。映写機は客席をのみこみ、カメラはセットに背を向けているというのに、その二つの極がいつももたれあいながら、地方はローマによって憶いだされることで意味を獲得し、ローマは地方からやってくる人びとのなかに意味を獲得し、両側に棲む怪物じみた人間たちのはざまで同じ神話が生まれ、それが『甘い生活』のアニタ・エクバーグの巨大な女神となって、そのまわりを回っている。フェリーニの仕事が狙っているのは、この発作的な神話を明るみに出し位置づけることであり、その中心にあるのが、さまざまな原型が螺旋状にひしめきあう『81/2』における自己分析なのだ。」
まさに、目の覚めるような卓見がちりばめられたこの美しいエッセイを読み返しながら、私は、カルヴィーノが、シナリオライターとして関わった二本の作品があったことを思い出した。
一本は、フォルコ・クィリチ監督の『チコと鮫』(62)、もう一本は、『ヴォッカチオ70』(62)の第一話、マニオ・モニチェリが監督した「レンツォとルチアーナ」である。
このオムニバス大作は、深夜、巨大な女神アニタ・エクバーグがローマの街を闊歩する、フェリーニ篇の「アントニオ博士の誘惑」ばかりが取り沙汰されるが、日本では劇場公開されなかった職人モニチェリのパートも、実に愛すべき小品である。
実は、最近、初めてこの「レンツォとルチアーナ」を見て驚いたことがある。工場に勤めるカップルが、職場結婚を禁止されているために極秘で結婚式をあげたものの、発覚して会社をクビになる。夫は夜間勤務の工場で働き、妻は、夫が早朝、帰宅する時刻に、目覚まし時計と共にベッドを起きだし、コーヒーを用意し、あわただしくキッスをかわしながら、仕事へ出かけて行く。残された夫は、ベッドに入ると、片側の、今しがたまで妻が寝ていた、その躰のかたちをとどめたままの温かい窪みのなかで、顔を枕にうづめ、妻の薫りにくるまれるようにして眠りにつくのだ。
このエロティックなラストシーンを見ながら、私は、カルヴィーノの傑作短篇集『むずかしい愛』(福武書店、のちに岩波文庫)のなかの名篇「ある夫婦の冒険」の忘れがたいエピソードがそのまま再現されているので、思わず、微苦笑してしまった。
イタロ・カルヴィーノは、名著『なぜ古典を読むのか』(みすず書房、のちに河出文庫)のなかで、「古典とは、読んでそれが好きになった人にとって、ひとつの豊かさとなる本だ。しかし、これを、よりよい条件で初めて味わう幸運にまだめぐりあっていない人間にとっても、おなじくらい重要な資質だ。」と書いている。この古典についての見事な定義は、イタロ・カルヴィーノの作品にそのまま当てはまるように思えるのである。
イタロ・カルヴィーノの傑作短篇集『むずかしい愛』(和田忠彦訳・岩波文庫)