2020.09.23笹本恒子さん

笹本恒子さんと僕
・今月9月21日は敬老の日であった。昨今、元気なお年寄りが多くなり、皆さん人生を楽しんでいるのは嬉しい限りだ。しかし、僕も含め長引くコロナ禍の影響で行動がどうしても制約されてしまうのは、残念なことである。僕の知り合いにもとびきりの元気印の方がいる。男性では僕が敬愛してやまない洋画家の野見山暁治さんを真っ先に挙げたい。野見山さんは、今年12月17日、御年百歳の大台に乗るはずだが、今も現役で画を描き続けておられるのだから凄い。素晴らしいバイタリティである。生涯現役とは野見山さんのような方をいうのであろう。僕など野見山さんより20歳近く年下なのに、病気の後遺症もあって足元も覚束ないのだから情けない。野見山さんは『四百字のデッサン』で日本エッセイスト・クラブ賞を受賞しているように、文章もひょうひょうとして味わい深いものがある。月刊誌『美術の窓』(生活の友社)に2003年12月号からというから、17年にもならんとする連載エッセイ《アトリエ日記》は、僕がいつも楽しみに愛読しているエッセイだ。野見山さんは、最近のアトリエ日記で「追悼文ばかり書かされているようで堪らん」と書いておられた。追悼文を依頼されるのは、親しかった証でもあり、残された者の義務として仕方がないのではないか、とも思える。とにかく、野見山さんのエッセイを毎月楽しみにしている読者が全国にたくさんいるのだから、もっともっと書き続けていってほしい。

地下鉄神宮前駅「いつかは逢える」(野見山暁治 2008年)
・さて女性では、なんといっても日本初の女性報道写真家・笹本恒子さんを挙げたい。今年、御年106歳になられるはずで、女性活躍社会のお手本のような方である。好奇心を大切にし、アンテナを張り巡らし、率先して行動してきた。清流出版を立ち上げた頃の僕は、月刊『清流』に続き、出版部門をスタートさせようと思っていた。出版分野としては、海外翻訳物、文藝エッセイ、実用書、小説、童話などを候補に上げた。更には僕が好きな芸術分野の出版物も柱として考えていた。芸術分野といっても広い。書道や洋画・日本画などの画集、美術エッセイ、写真集などがその候補であった。ちょうど創業から3年ほど経った1996年、写真集の著者候補として恰好の人物にお会いできた。それが笹本恒子さんであった。笹本さんはその頃、あるテーマをもって写真を撮り続けていた。その対象への思いをこう語ってくれた。「女性の権利がまだ保障されていなかった明治時代に生まれ、大正、昭和と走り抜けてきた、この人たちの苦労を残しておかなければならないとの強い思いから、明治生まれの女性を撮り続けてきました」と。

弊社応接室にて
・僕は日ごろから、女性の潜在的なパワーには感服していたこともあり、そのテーマに心を惹きつけられた。写真を見せてもらって、すぐに出版することを決め、笹本さんには写真選びと添える説明文をお願いした。こうして写真集が完成の運びとなった。弊社刊行の『きらめいて生きる 明治の女性たち――[笹本恒子写真集]』はこうして世に出たのである。明治という時代に生まれ、大正、昭和と生き抜き、時代を牽引してきた各界の女性たちは輝いていた。笹本さんは、そんな女性たち60人に直接会い、毅然として生きる姿を活写してきたのである。お恥ずかしい話だが、題字は元気だったころの僕が書いたものだ。
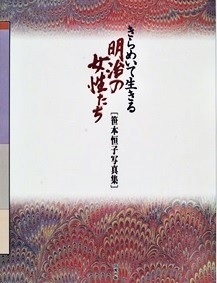
初版の表紙である
ちなみに登場人物は、歌手、小説家、詩人、随筆家、美容家、政治家、経営者、デザイナー、舞踊家など、極めて多岐にわたる。具体名(敬称略)を挙げれば、宇野千代、淡谷のり子、加藤シヅエのほか、佐多稲子、杉村春子、沢村貞子、秋野不矩、住井すゑ、丸木俊、飯田深雪、石垣綾子、井上八千代、北林谷栄、田中澄江、長岡輝子、三岸節子、吉行あぐりの諸氏など錚々たる女性たちが並ぶ。判型もA4変形を採用したので大きく掲載することができ、迫力のある写真集となった。これをきっかけに笹本さんには、何冊か弊社から単行本を出させて頂いた。『夢紡ぐ人びと――一隅を照らす18人』(2002年)、『ライカでショット!――お嬢さんカメラマンの昭和奮戦記』(2002年)、『昭和を彩る人びと――私の宝石箱の中から一〇〇人』(2003年)など、弊社の出版物のラインナップに華を添えて頂いた。
・簡単に笹本さんのプロフィールを紹介しておく。1914年、東京都の生まれ。日本初の女性報道写真家として知られる。1940(昭和15)年、財団法人写真協会に入社。社会派の写真を手掛ける一方、旺盛な行動力で明治の女性たちを手弁当で追いかけ、紹介してきた。終戦後、写真家として復帰し、国内で起こった話題・事件の女性たちを撮り、数多くのグラフ雑誌に掲載したが、活動の場であった写真グラフ誌の多くが廃刊され活動を休止した。約20年間の沈黙を破り、1985年に71歳で国内を代表する著名な女性有名人を集めた写真展「昭和史を彩った人たち」で再び写真家として復帰した。2001年、第16回ダイヤモンドレディー賞、2011年には吉川英治文化賞、2014年、第43回ベストドレッサー賞・特別賞、2016年、米国のルーシー賞(英語版)(ライフタイム・アチーブメント部門賞)など数々の賞を受賞している。2016年3月、それまでに撮影した100点の写真を長野県須坂市に寄贈。2018年、東京都名誉都民に顕彰される。
また時に笹本さんは、自費出版したという写真集を、売り込みに来社されたこともある。僕は笹本さんからその本が出版に至った経緯を聞くに及び、意気に感じて数十冊購入したことがある。それが『素顔の三岸節子 60年の想いをこめて』である。自費出版してまで三岸節子さんとの約束を守った、笹本恒子という人間に惚れ直したものだ。笹本さんは、1988年にフランスのヴェロンに三岸節子さんのアトリエを訪ねた際、絵と人となりを伝える写真集を出版するという約束をしたのだという。そのまま約束が果たせず、いつしか10年という月日が経ってしまったのだった。

自費出版(1998年)
二人の初めての出会いは、1938年にまで遡る。笹本さんは写真家になる前、画家を志していたことがあり、絵を見てもらおうと三岸節子さんを訪ねたことがあった。フランスはパリから南へ130キロ、ブルゴーニュ地方のヴェロン村の三岸邸を訪ねた時には、その時からすでに半世紀近くも経っていた。三岸さんはこう言った。「そういえば、初めて絵を持って私のところにいらした時は、あなたはお下げ髪の少女だったわね。確か新聞社の偉い方の紹介で……」。笹本さんは、三岸さんの記憶力の良さにびっくりしたらしい。そんなに長いお付き合いがあり、約束を果たせなかった笹本さんは、自らの不甲斐なさに切歯扼腕していたことだろう。僕は見本を見て、写真はもちろん、添えられた文章にもほだされた。読むほどに、三岸節子画伯と笹本恒子さんの人間と人間の深い絆がひしひし伝わってきた。僕は編集者が作家とお付き合いしていく上での一つの形として、弊社の編集者にも是非読ませたいと思い、1冊ずつ配ったことを覚えている。
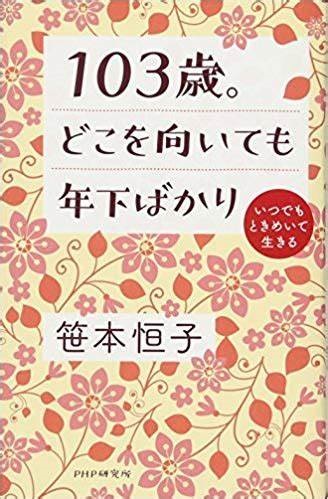
PHP研究所刊(2017年)
・笹本さんは長らく都内の高層マンションに一人住まいをされていたが、自宅で転んで大腿骨を骨折してしまう。立ち上がろうと手を突いた時に、手首も骨折してしまう。あまりの痛さにそのまま気を失い、22時間倒れたままだったという。この時の笹本さんの情況は僕にもよく分かる。僕も似たような体験をしたからだ。僕は、清流出版を立ち上げて以降、編集のほか経理や広告、営業等も見ていたので忙しく、ウィークデイはフェアモントホテル(当時)を定宿にし、週末だけ八王子の自宅に帰るという生活をしていた。午前1時前、ホテルに入浴して浴槽から上がってきて、そのまま脳出血で倒れてしまう。笹本さん同様、ほぼ一昼夜というもの倒れたままであった。不審に思った社員からの問い合わせで、ホテル側がカギを開けて発見されることになった。
笹本さんの場合も、翌朝、取材で訪れた方が異変に気づき、なんとかカギを開けて発見され、そのまま入院し緊急手術となった。そんな笹本さんに更なる悲劇が襲う。なんと今度は、入院先の病院のベッドから転げ落ち、反対側の大腿骨も骨折してしまう。両方の大腿骨を骨折してしまっては、歩けるわけがない。車椅子の生活となり、一人暮らしを諦めて100歳で鎌倉の老人ホームに入所することになった。老人ホームは安心・安全な場所として重宝されるが、バリアフリーで何もかも介護の人がやってくれるので、身体を使わなくなり筋力低下は否めない。意識しないと頭も使わなくなり、老化がますます進行することになる。笹本さんはそんなことは百も承知だった。自分を鼓舞する方法を知っている。
・「ここに移ってからすぐに、全身が映る鏡を買いました。いつも身だしなみには気をつけなければね。壁には大好きなゴッホの『ひまわり』の絵を飾りました」。気持ちよく暮らしたい、の思いからだという。好奇心を持って前向きにというのが、笹本さんの真骨頂だ。仕事に生き、ときめきの対象を見つける名人でもある。暮らしている老人ホームの最高齢なのはもちろん笹本さんだ。「一番忙しくしているのも私かもしれません。とにかくボーッとしている時間がないの。いつどうなっても不思議ではないから、やり残した仕事を完成させないと、おちおち死ねません」。と意気軒高である。『好奇心ガール、いま97歳』の著書もある笹本さん。今日という日を充実して過ごしている。こんな前向きな生き方、次代の若者たちに是非学んでほしいものである。
