十二月十日、小沢昭一さんが亡くなった。享年八十三。十年ほど前に前立腺がんが見つかり、治療を続けていたことは知っていたが、それでも今、何とも形容しがたい喪失感に襲われている。
それは、多分、私が初めて名前を覚えた喜劇人が小沢昭一さんであったせいかもしれない。
一九六一年、私が小学校に入ったばかりの頃に、NHKの日曜夜八時から『若い季節』が始まった。淡路恵子が社長の「プランタン化粧品」を舞台に繰り広げられる洒落たコメディで、毎週楽しみに見ていた。この会社の社員にはハナ肇とクレイジー・キャッツ、ダニー飯田とパラダイス・キング、黒柳徹子、いつも白いタートルネックのセーターを着ている古今亭志ん朝などがいて、皆が行きつけの小料理屋の板前が渥美清だった。
今、考えでも信じがたいような豪華なメンバーである。そして小沢昭一さんは、たしかケチクマという渾名で、ケチでいつもぶつぶつ文句ばかり言っている若手社員を演じていた。その偏屈な、アクの強い、嫌われ者みたいな独特のキャラクターが毎回面白くてならず、子供心にも強烈な印象として焼き付いたのだった。
思えば、当時は、土曜の夜にNHKの『夢で逢いましょう』を見て、日曜日の夕方には民放の『てなもんや三度笠』と『シャボン玉ホリデー』を続けて見た後、『若い季節』にチャンネルを合わせるという黄金のルーティンが出来上がっていた。私のエンターテインメントに対する<基礎教養>は、この小学生の時に熱中したテレビドラマ、バラエティによって形成されたのは間違いない。
次に小沢昭一に出会ったのは、一九六九年に刊行された『私は河原乞食・考』(三一書房、のちに岩波現代文庫)である。ストリップから大道芸、香具師、ホモセクシュアル、落語など後の「日本の放浪芸」研究につながる私的な芸能論ともいうべき小沢さんの最初の著作であった。
この本を読んだきっかけは、その頃、毎週欠かさずに聴いていた永六輔の深夜放送「パック・イン・ミュージック」の影響が大きい。永六輔は、当時、熟読していた雑誌『話の特集』に「芸人その世界」を連載中で、「パック」にも小沢昭一をゲストに呼んで、この本を絶賛していたからだ。
たしか、中学校の卒業文集に「差別される芸について」などという身の程知らずの文章を書いたのを憶えているが、大半は、この小沢昭一さんの本の受け売りだったと思う。土台、中学生に理解できる本ではなかったのだが、そんないっぱしの芸の通人気取りのティーンエイジャーに、冷水を浴びせたのが、一九七二年に出た小林信彦さんの『日本の喜劇人』である。
当時、まさにむさぼるようにして読んだこの本には「上昇志向と下降志向」という章があり、渥美清と小沢昭一が対照されて論じられているのだが、次のような一節に、高校生だった私は心底驚いたのだ。
「ディテールにおいては鋭いものをもちながら、このエッセイ集(『私は河原乞食・考』)が、もう一つ私に迫らないのは、こういうところである。
『……新劇は新劇の伝統をまず作り上げることが急務でありましょう。しかし、それはそれとして、やはり、日本人のわれわれは、日本の伝統芸能に関心が向かざるを得ない。……。』
この<それはそれとして>というのが、どうしてもわからない。
<新劇>人としての小沢昭一がいる。一方に、伝統芸能に心を寄せる小沢昭一がいる。これをつなぐのが、<それはそれとして>では、マズいのではないか。河原乞食・伝統芸能――それらを意識した小沢昭一が、<新劇>(でなくてもいい。芝居でいい)のなかで、どういう演技を見せるかということによって、私たちは、小沢昭一の、<それはそれとして>といったアイマイなものではない方向を初めて知りうるのである。
小沢昭一の下降志向――ストリップや見世物やホモへの偏執――が、ある種のスノビズムやノヴェルティ(新奇さ)やモダニズムの裏返し(ブロードウェイ・ミュージカルへの憧れが、一転、大阪の角座の漫才に変る!)でないことは、よく納得できる。だが、小沢昭一には、どんなに下降しようとしても、しぜんに上昇してしまうようなところがある。
一方、渥美清は、いくら上昇しても、彼の内部の、白骨が散らばっている眺めから、自由になれないところがある。
昭和四十四年に、小沢が『私は河原乞食・考』を出版し、渥美が『男はつらいよ』で再起したのは、ほとんど、象徴的といってもいい。」
『日本の喜劇人』が掛け値なしの名著であるゆえんは、こういう厳しくも鋭い本質的な考察が、さりげなく随所に散見されるところにある。
別段、小林信彦さんの指摘を内心で受け止めたわけではなかろうが、以後の小沢昭一さんの仕事を見渡すと、映画出演がめっきり減り、新劇俳優としては、劇団『芸能座』、『しゃぼん玉座』を主宰するいっぽうで、ライフワークのCD・DVD『日本の放浪芸』シリーズを纏め上げ、『放浪芸雑録』、『ものがたり 芸能と社会』(新潮社)などの大著を次々に物し、近年は、まるで市井の民俗学者のような風格と面影があった。
『日本の喜劇人』のほぼ三十年後に書かれた小林信彦さんの傑作評伝『おかしな男 渥美清』(新潮文庫)の巻末に、小林さんと小沢昭一さんの「渥美清と僕たち」という、まさに見巧者同士による至高の芸談ともいうべき対話が載っているのは、一種、感動的でさえある。
結局、俳優としての小沢昭一の魅力を探ろうとすれば、一九五〇年代後半から六〇年代の初頭につくられた日活のプログラム・ピクチュアになるのではないだろうか。
中平康の『牛乳屋フランキー』のライバルの牛乳配達屋、川島雄三の『貸間あり』の万年浪人生、『幕末太陽傳』の貸本屋・金蔵、『しとやかな獣』の金髪のインチキ歌手、主役では西村昭五郎の『競輪上人行状記』の競輪狂いの果てに寺を失ってしまう破戒僧などが、すぐさま思い浮かんでくる。
数年前だったか、ラピュタ阿佐ヶ谷で「春原政久特集」が組まれた際に、小沢さんは主演作の『猫が変じて虎になる』が上映されると知るや、何度も通いつめたという話をきいたことがある。私は、テレビの『若い季節』と並行して撮られていた、この時代の小沢さん主演の喜劇映画をほとんど見ていないので、ぜひ、どこかの名画座でまとめて特集上映してほしいものだ。
そういえば、この頃、小沢昭一さんが「やっときたか!」と欣喜雀躍した企画がある。川島雄三監督が小沢昭一主演で、山口瞳の直木賞受賞作『江分利満氏の優雅な生活』を映画化するという話である。すでにシナリオも完成しており、傑作『しとやかな獣』と同様に、主人公の社宅の一室からキャメラが一歩も出ないという実験的な作品になるはずであった。
しかし、周知のように、一九六三年、川島監督の急逝により、『江分利満氏の優雅な生活』は、代わりに岡本喜八監督がメガホンをとって、小沢さんではなく、小林桂樹の主演で映画化された。
今では、『江分利満氏の優雅な生活』は、岡本喜八監督の代表作として、その評価はゆるぎないものになっているが、それでも、私は、時々、川島雄三と小沢昭一のコンビによる幻のヴァージョンも、ぜひ、見て見たかったな、と思う。
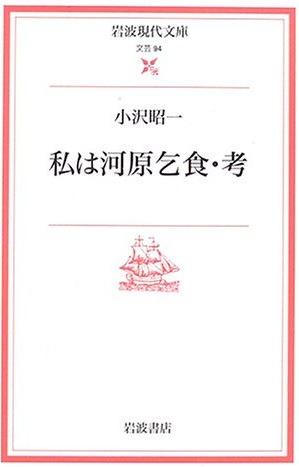
小沢昭一著『私は河原乞食・考』(岩波現代文庫)


