2019.08.29渡部昇一、堺屋太一、竹村健一、深田祐介 (サンピンイチスケ)の各氏

深田祐介さんと僕
・「サンピンイチスケ」という言葉をご存じであろうか。1970年代からマスコミ界を席巻した四人の売れっ子評論家・作家のことである。具体的には、渡部昇一、堺屋太一、竹村健一、深田祐介の四人。三人の名前の最後に一がつくことからサンピン、深田祐介のスケを合わせ「サンピンイチスケ」と命名されたものだった。テレビ、雑誌、新聞などにこの四人はよく登場し、マスコミ露出度もかなり高かった。当然のことながら、知名度が高く人気があっただけに、著者として執筆依頼が殺到したのもよくわかる。この四人の単行本を出せば、大いに話題にもなり売れたからである。
僕が古巣ダイヤモンド社に在籍し、雑誌部門から出版局に移ったのが1980年、ちょうど40歳だったが、そのころ、「サンピンイチスケ」人気はピークを迎えていた。今回、この「サンピンイチスケ」について書きたいと思った動機だが、渡部昇一さんが2017年 に86歳で、堺屋太一さんが2019年2月8日に83歳で、竹村健一さんが 2019年7月8日に89歳で、深田祐介さんが2014年に82歳で死没ということで、一世を風靡したあの「サンピンイチスケ」は、四人目の竹村健一さんの死によって、全て黄泉の国の住人となってしまったからである。
・簡単にこの四人を紹介しておく。渡部昇一さんは、1930年山形県生まれ。1955年、上智大学博士課程を修了。英語学が専攻であった。ドイツ・イギリスに留学。2001年、上智大学の名誉教授となっている。渡部昇一さんが大ブレークするきっかけとなったのは、1976年刊行の『知的生活の方法』であった。累計部数118万部を超えて、講談社現代新書のベストセラーとなった。頭の回転を活発化し、オリジナルな発想を楽しむ生活の仕方を提案したもので、読書の技術、カードの使い方、書斎の整え方、散歩の効用、通勤時間の利用法、ワインの飲み方、そして結婚生活等々、著書自身の体験を通しての柔軟な発想が受けたものだった。渡部さんには、古巣ダイヤモンド社で、月刊誌の取材のために数回会ったことがあった。清流出版を立ち上げてから、直接、お姿を拝見したのは、ビジネス茶を提唱した荒井宗羅さんの著『和ごころで磨く―ビジネスに生かす“茶の湯の精神”』(1997年6月刊)を弊社から刊行した時、出版記念パーティであった。ゲストとして招かれていたのである。その時以来、雑誌の連載をお引き受け頂くなど、渡部さんと僕との長いお付き合いが始まった。

講談社現代新書の大ペストセラー
渡部昇一さんの交友関係は広い。特に、堺屋太一・竹村健一の両氏とは交流が深く、3人で講演会を催したり共著を出版したり、『三ピン鼎談 平成日本の行方を読む』(1990年2月、太陽企画出版刊)を刊行したこともある。また、谷沢永一さんとは共に知られた蔵書家であり、思想的にも共感できることが多かったらしく、たくさんの共著を出している。渡部さんはテレビでもよくお顔を拝見した。竹村健一さんとの掛け合いは特に面白かった。「竹村健一の世相を斬る」(フジテレビ)にゲスト出演していたのが懐かしく思い出される。また、自身の番組も持っていて、石原慎太郎、加藤寛、田久保忠衛、岡崎久彦といった著名人を招いての対談番組「渡部昇一の新世紀歓談」(テレビ東京)、渡部昇一の「大道無門」(日本文化チャンネル桜)もやはり対談番組で、各界の著名人を招き、歴史、政治、時事問題などを語り合うホスト役を務めておられた。
堺屋太一(本名・池口小太郎)さんは、1935年大阪府生まれ。東京大学卒業後、通産省の官僚となり、経済企画庁長官、内閣特別顧問、内閣官房参与などを歴任した後、小説家、評論家となった。当時ダイヤモンド社は霞が関1丁目にあり、通産省の隣のビルだった。噂では池口小太郎さんは若手の官僚だが、実に魅力的で面白い人物だとのことで会いに行った。僕は、所属している「経済週刊誌 ダイヤモンド」の新米記者として、「通産省として何かエポックメイキングなことはないですか?」と尋ねた。その時は会話に出なかったが、大きなイベントを成功させることになる。池口小太郎さんは、1970年の「大阪万博」の企画・実施に携わるのだ。来場者が世界中から実に6422万人となり、大成功であった。この頃、堺屋さんはまだ三十代の若さ、小松左京さんや丹下健三さんをはじめ、東大や京大の先生などを強引にかつ粘り強く引っ張っていった手腕は特筆に値する。
大阪万博にはしっかりとしたコンセプトと哲学があり、後の携帯電話やドーム建築につながるような、新しい世界を見せてくれたのではないか。堺屋さんには、鬼気迫るような面があり、自ら考え、自ら動いた。平気で24時間働き続けるようなバイタリティの持ち主であった。また、博覧強記の人であり、それでいて愛敬があったので多くの池口ファンがいた。時代の節目を鋭く切り取る言葉でも注目され、特に『団塊の世代』という言葉は、本の内容とともに衝撃をもって迎えられた。2000年以降の少子高齢化社会を言い当てる警句ともなった。ちなみに1975年には『油断!』が、1976年には『破断界』が出版され、本の売れ行きと共にこの言葉も話題を呼んだものだった。


竹村健一さんは1930年大阪府生まれ。京都大学英文科卒業後、フルブライト留学生として米エール大、シラキュース大大学院で学び、『英文毎日』の記者となった。その後、山陽特殊製鋼調査部長、追手門学院大助教授を歴任した。「保守派」の論客として知られ、1979年から1992年までフジテレビ系で放送された「竹村健一の世相を斬る」で司会を務め、関西弁の語り口が人気を博した。日本テレビ系「世相講談」では現・東京都知事の小池百合子さんがアシスタントを務めていた。「モーレツからビューティフルへ」「デリーシャス」などの流行語を生み出したほか、情報を手帳1冊に集約する「これだけ手帳」を自ら提案し発売もしている。「僕なんかこれだけですよ」と本人が語ったCMを覚えている方もおられるだろう。50歳当時、テレビ、ラジオのレギュラー番組が月95本、著書200冊に達するなど多忙を極めた。当人の弁によれば、ピーク時には、「口述筆記で一時間五十枚ほど」書いた、というから驚異的なスピードであった。
深田祐介(本名・雄輔)さんは1931年東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業。日本航空広報部に勤務したサラリーマン作家として知られ、1976年に『新西洋事情』で大宅壮一ノンフィクション賞、1982年に『炎熱商人』で直木賞を受賞している。日本航空を退社して後は、作家として創作活動に専念した。1987年に『新東洋事情』で文藝春秋読者賞を受賞しているが、サラリーマン生活と海外駐在経験が長かったことから1976年『西洋交際始末』、1977年『貿易戦争と中産階級』、1979年『革命商人』などに代表されるように海外ビジネスや企業小説が多い。
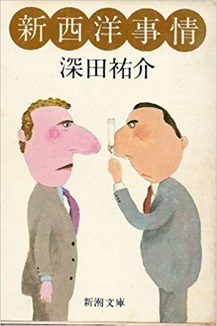

・僕は1980年に、ダイヤモンド社の雑誌部門から出版局へ転属し、1992年の初頭に辞め、独立して小出版社をすることになるが、その間、幾多の単行本を手掛け、多くの著者と交友関係を結ぶことができたのは僥倖であった。最初僕は、昭和天皇のご学友・藤島泰輔さんの編集担当となった。藤島さんと僕とで仕掛けたポール・ボネのシリーズは売れに売れ、さらには文庫化の権利も他社に売れた。藤島さんは多額の印税を手にすることになり、フランスのパリ16区に豪邸を取得したり、ランニングフリーなど競走馬を持つことになった(藤島さんの薫陶を受けた僕の趣味が「競馬」となった)。パリの住まいは、元NHKの花形ニュースキャスター磯村尚徳さんが日本文化会館初代館長になった際、リースされることになった。その話は直木賞作家・深田祐介さんも知っていて、お会いした時にこの話で盛り上がったことが懐かしい。深田さんは僕と多くの人脈も重なるし、同じ身体障害者の一級同士ということで話が弾んだものだった。

竹村健一さんの翻訳本
・ここで僕は竹村健一さんの話をしておきたい。1967年、竹村さんは『マクルーハンの世界』(講談社)という本を翻訳し、マクルーハン理論を日本に初めて紹介した人物でもあり、尊敬をしていた。マクルーハンは、特にテレビが現代に及ぼした影響についての研究で知られた人である。実は僕が出版局に移る前の1977年にダイヤモンド社から竹村健一さんの『日本の常識は世界の非常識!?』という本を出ており、販売実績も良かった。僕も出版局に移るに当たって、絶好調だった竹村健一さんの本を出したいと思っていた。だから、アポイントを取り、赤坂にあった竹村さんの事務所に伺った。1980年1月のことである。僕は温めていた単行本の企画案を提示して、執筆依頼をしたのだが、執筆はなんとかなりそうなのだが、どうしても条件面で折り合えなかった。
竹村さんが主張する印税率は、出版界の常識からすれば、考えられないほどであった。最低でも4割増し(14%)、できれば倍近い率(20%)でと要求してくる。竹村さんは、関西弁でなぜそうなるのかをまくしたてるのだが、理論的には分からないわけではない。自身が広告塔になっているから、出せば十分売れる本になる。広告宣伝費込みで考えれば安いものじゃないか、ということになる。そしてついには、手元にあったノートを見せ、他社で出した本の初版部数、印税率等をつまびらかに披露されるに及んで、僕は切れてしまった。「そんな高額な印税を払ってまで出すことはできない」、ときっぱり断ってしまった。帰社してから、営業サイドからは恨まれることになったが、こればかりは受けられなかった。あの丁々発止のやりとりは、今でも懐かしく思い出される。

竹村健一著(1977年 ダイヤモンド社刊)

ドラッカー博士と竹村さんとのツーショット(ダイヤモンド社)
・竹村さんとはその後、前述した荒井宗羅さんの『和ごころで磨く』出版記念パーティでお会いし、何のわだかまりもなく気持ちよく挨拶を交わした。それにしても盛況だった荒井宗羅さんの出版パーティ。船井幸雄さん、竹村健一さん、ジェームス三木さん、細川隆一郎さん、浅草寺の京戸慈光師、渡部昇一さんはじめ、綺羅星のごとく宗羅ファンが押しかけた。
宗羅さんに、竹村健一さんと出会ったきっかけを聞いてみると、なるほどとうなずけるものだった。初めて会ったのは、宗羅さんがプロデューサー兼アートディレクターとして関わった新宿の料亭だという。ビルの最上階にあった100坪以上の料亭には、露地もある本格的な茶室から、当時メディアを騒がせた黄金の茶室や10室ほどの個室もあった。宗羅さんは、この料亭全てのコンセプトメイキングと若い仲居さん達の接客教育、集う政財界、文化人に対するお茶のもてなしの仕方から、日本文化絡みのレクチャーまで広範囲にわたったという。

出版パーティで荒井宗羅さんと
たまたまこの料亭を訪れた竹村さんが、この料亭のしつらえや接遇などに感服し、プロデュースした宗羅さんに関心を抱いたということらしい。その時の当意即妙の宗羅さんとの会話が気に入ったらしく、帰り際にねぎらいの言葉を掛けてくれたという。以来、宗羅さんは、竹村さんの自宅で催されたお花見の会や奥方の個展に招かれるようになる。会えば、竹村さんは、トレードマークのパイプをふかしながら、主に海外と日本との比較文化や、英語の特殊な表現法などを教えてくれた。出版記念パーティの時も、竹村さんは開口一番、「宗羅さん、一流の著名人がみんな集まったな。大したもんだ」と褒めてくれたそうだ。宗羅さんならさもありなんである。僕が関わりをもった著者が、世界に羽ばたいていくのを見るのは、編集者冥利に尽きるというものだ。荒井宗羅さんのさらなるご活躍をお祈りしたい。
