2018.11.29山内邦雄さん、田村紀男さん、佐藤徹郎さん
●山内邦雄さん
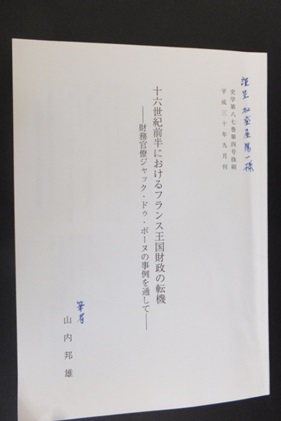

・11月某日、僕の小学・中学校の同級生であった方から論文(小冊子)と書状をいただいた。この論文に目を通して見ると、ここ8年来、山内さんが慶応義塾大学大学院で西洋史を勉強され、その成果をまとめたものだった。慶応三田史学会の研究誌『史学』(第87巻第4号、平成30年9月刊)で掲載されたもので、タイトルは『16世紀前半におけるフランス王国財政の転機――財務官僚ジャック・ドゥ・ボーヌの事例を通して――』となっている。興味を引かれたものの、僕が詳しい世紀の話ではなかった。中学校の同級会で山内さんと会った時は、通り一遍の話しかしていない。山内さんは定年まで、みずほ銀行パリ支店に駐在し、その後、縁故の企業で働いていたことは知っていた。そして70歳を期して仕事を終え、人生の総仕上げとして好きな学問に邁進されたのであろう。今回、78歳にして、慶応三田史学会で論文として集大成したのだ。僕としては、山内さんの不屈の向学心、自己研鑽、その生き方に「あっぱれ!」という誉め言葉しか浮かばなかった。
・早速、その論文だが、浅学菲才の上に僕が得意とする世紀の話ではないので、ほんのさわりだけに留めおくことにする。
16世紀前半→フランス王国財政→財務官僚ジャック・ドゥ・ボーヌを紹介したい。まず、冒頭の《1527年8月12日、元王国財務責任者ジャック・ドゥ・ボーヌ(1452―1527)がパリ・モンフォーコン刑場で絞首刑に処せられた。国王や王太后の信頼を得て、平民出身ながらサンブランセ卿という地位まで賜った彼の処刑は、フランス社会に大きな反響を呼んだ》という文章が目を引いた。論文の冒頭に、これから扱う主人公が亡くなったことから始めている。導入部の見事な掴みである。
彼を死刑に追い込んだものは何であったのか、それが、山内さんの論文では、《第1章で研究史を概観し、第2章で中世の枠組みを残すフランソワ1世治世初期の財政制度を考察した後、第3章でジャック・ドゥ・ボーヌの上昇と財務官僚としての活躍を取り上げ、第4章で彼の失脚と背景、さらに裁判を分析する》構成を採用している。全体像を俯瞰して、読者が分かりやすい章立てになっている。
・この後、山内さんの論文は、ジャック・ドゥ・ボーヌの生涯を通して、フランソワ1世治世初期のフランス王国財政の変化を詳細に論じた。彼は何故、極刑に処せられたのだろうか。当時のフランソワ1世が置かれた状況が、大きく影響していたと考えられる。《フランソワ1世にとり、豊富な軍事費を持つためには、財源の拡大だけでなく、横領・不正の疑いのある財務官僚を追放して、新しい財務官僚を構築することが急務であり、制度改革を徹底するためには、ジャック・ドゥ・ボーヌの処刑が妥当と考えた……云々》
論文中から興味深い段落を紹介してみよう。
《それではリヨンの銀行家のフランス国王向け融資残高はどの程度あったのだろうか。1522年2月末王令にあるジャック・ドゥ・ボーヌへの債務157万リーヴルが一つの指標となろう。……この中には60万リーヴルの国王のナポリ資金と王太后の個人資金10万リーヴルが含まれているので、純債務額は87万リーヴルとなる。……この金額はリヨンの銀行家の国王与信限度に近づきつつあったのではないだろうか。王の返済遅延により、銀行家自身の資金繰りも悪化し経営は苦しくなっていた。加えてピコッカの敗戦は、フランス王国に対する彼らの見方を変え、国王に対する融資態度を慎重にさせていた。かくして王の変わりやすい外国人施策、寄付金の延滞、限度額に近い債務残高、敗戦による国王与信への危惧は、1523年以降リヨンのフィレンツェ人銀行家の融資を停止させたのである》――
・この他にも、まだまだ興味深い話が出てくるが、ここで引用するには長過ぎるので、ひとまず終わりにしたい。いずれにせよ、いずこも国王に忠実な財務官僚だったがゆえに責任がのしかかり、結局は、詰め腹を切らされる羽目になっている。歴史は繰り返される、としかいいようがない。
山内さんの論文は、僕にとって大いなる刺戟となり、今から60年ほど前、僕も大学で勉学に励んでいた頃のことを思い出した。僕は早稲田大学のゼミで、増田富寿教授の指導を受けていた。増田先生は英独仏露の四か国語に堪能だった。卒論は、「世紀は問わず、外国の文献を使って、各々、興味を惹く経済史を論ぜよ」との課題だった。僕は「18世紀のフランス経済史」を選んだ。ゼミの仲間たちはそれぞれ、ドイツ語やロシア語のテーマを選んだ。だが、4年生の冒頭、増田先生はロシアからの要請で長期的にロシアに滞在を強いられ、ゼミなし、成績もなしの結果になった。僕は卒論にピッタリのアンリ・セーの原書を見つけ、張り切っていたが空回りに終わった。あの時、真剣に勉強していれば、山内さんの論文テーマももっと深く理解できたことだろう。
・山内さんといえば、お嬢さんの山内由紀子さんの翻訳本を、月刊『清流』で取り上げたこともある。その本は、『ひとりヴァイオリンをめぐるフーガ』(テディ・パパヴラミ作、山内由紀子訳、藤原書店刊、2016年)という本だった。アルバニア出身のヴァイオリニストが、共産主義政権下の母国からフランスへ亡命し、小説の翻訳などに活動の場を広げた波乱の半生をつづったものだった。由紀子さんは東京大学教養学部フランス科を卒業後、アメリカに渡り、ニューヨーク州立ファッション工科大学を卒業された才媛である。パリ、ルクセンブルク、ニューヨークで生活したこともあり、今後、そうした生活体験も生かして名翻訳家の道を歩まれるものと確信する。
また、山内邦男さんの兄上は山内太郎さんで、早稲田大学高等学院の僕の2年先輩にあたる。部活で「短歌研究会」に所属し、『蓮華』(れんげ)誌の同人であった。ある時、太郎さんから頂いた『蓮華』誌上に、河出書房の御曹司・河出朋久さんが短歌を詠み、それが掲載されていた。「河出まこと潰れるものか人々よ……」と、河出書房の第1次倒産に際した心情を吐露したものであった。この時、僕は、将来、就職先を考えた場合、出版業界は赤信号とまではいかないにしても、黄色信号が点っているかもしれない、と感じたものだ。
・それから7年の歳月が経ち、僕は就職活動の結果、映画会社と出版社に内定をもらった。しかし迷いに迷い、どちらか決めかねていた。困った末に僕は、内定した2社ともに辞退し、大学院に行きたいと方向転換をしようとしたのだ。すると大学の就職課では、「そのようなことをしたら、今後、早稲田大学の学生を採用はしてくれなくなる。どちらかに決めなさい」と大いに怒られ、結局、出版社のダイヤモンド社を選んだ経緯がある。7年前の高校生の時、出版社を避けたいと思っていたことは、すっかり失念していたのである。
・山内邦雄さんは、小・中・高・大学の友だちの中でも、特に好感度が高く、得難い親友だと思っている。そして同級会でお会いした時、山内さんが僕に言った言葉が忘れられない。「今日一日生きているのは、すなわちモーツァルトを聴けることだ」と言ったのだ。大のモーツァルトファンである山内さんは、演奏家も古今東西、モーツァルトの曲想を活かせる演奏家から選びたいと話す。僕もモーツァルトは大好きだが、山内さんのように、注目する演奏家が、新しいCDを出すたび購入して聴き惚れる情熱には、脱帽するしかない。
●田村紀男さん、佐藤徹郎さん
・ダイヤモンド社の社長をされたこともある田村紀男さんがお亡くなりになった。わが社の月刊『清流』で校閲を担当してくれている茂原幸弘さんが、「ダイヤモンド社に赴いた際、社内の提示で知った」と10月11日に伝えてくれたものだ。田村さんは手抜きせずに全力投球の人であり、遊びでも仕事でも、親しい仲間としてともに過ごしてきただけに、ポッカリと胸に風穴が開いたような寂量感に襲われた。
その知らせはこう続いた。「すでにお聞き及びかとも存じますが、ダイヤモンド社元社長の田村紀男さんが、9月25日に急逝されたとのこと。小生は、ダイヤモンド社に赴いた際に、社内の掲示で知りました。写真を添付いたします。そこにある通り、ご葬儀等は既にお身内で済まされたようです。ダイヤモンド社の社員から聞いた話では、田村さんはご自宅で、料理をしようとして、台所に向かって歩いている途中で、突然倒れられたとのこと。小生も田村さんには大変お世話になりましたので、この度のことは本当に驚いております。心より、ご冥福をお祈りいたします」
僕は、びっくりして、ダイヤモンド社で同僚だった佐藤徹郎さんに電話した。徹郎さんも葬儀が済んでから、ご家族からの知らせがあったそうで、葬儀には出ていないという話だった。
・田村さんは昭和15(1940)年、秋田県秋田市の生まれ。秋田高校から早稲田大学を卒業後、ダイヤモンド社に入社した。出版部長、取締役を経て、平成12(2000)年に代表取締役社長になっている。4年後、社長を退任して出版プロデュース業や講演をなさっていた。田村さんの生い立ちでは、直木賞作家の和田芳恵さんの甥筋であることが特筆される。そして、その和田芳恵さんの娘・陽子さんは、田村さんのいとこだが、詩人・筑摩書房取締役の吉岡実さんに嫁いだ。僕は、田村さんと吉岡実さんとの関係をまったく知らずに、吉岡さんとは何回も同席する機会を得た。
その機会は、僕の先輩であった龍野忠久さんや新潮社の『藝術新潮』編集長・山崎省三さんが呼びかけたものだった。構成メンバーとしては、美術評論家・瀧口修造さん、詩人・吉岡実さん、美術評論家・大島辰雄さんがトリオで集まることが多かった。青木画廊の展覧会を観た後、他の銀座の画廊や展覧会、さらに各種イベントに集う時に、よく声をかけられた。コーヒー、食事はもとより、特にお酒が入ると大いに談論風発し、楽しい集まりであった。このメンバーでは、僕だけが若輩者で、可愛がられ、引き立ててもらった。なんという幸せな一時を過ごしたことだろう。
・田村さんは毎月、ダイヤモンド社近くの虎ノ門書房で購入した、『群像』、『文学界』など文芸雑誌を購読されていた。仕事上では経済・経営的なものを扱うので、文芸誌にくつろぎを感じていたと思われる。周りの小説家や詩人といった文学系の濃い血がうずいたのではないか。また、月刊『清流』で創刊号からつい最近まで長く執筆を続けてくれた茶道家・鈴木晧詞さんのことを、30代初めに僕に紹介してくれた。鈴木さんは、日本大学藝術学部を卒業し、和田芳恵さんに師事された。その後、鈴木さんは、曽野綾子さん、三浦朱門さんとの知遇を得ている。
田村さんが社長になって3年後の平成15(2003)年、秋田高校の同窓会で『出版業界事情あれこれ』と題し、講演をされている。このことを僕はインターネットで検索して見た。その同窓会メンバーの中に、弊社からも1冊出させていただいた「若い根っこの会」の加藤日出男さんのお姿を観た。加藤さんは、進学された東京農業大学で「大根おどり」を創案した方だ。
・そして、田村さんはお亡くなりになる4か月前、秋田高校東京同窓会報に特別寄稿として『秋田出身の文学者たち』と題し、文を寄せられた。その中で、新潮社を創業した佐藤義亮氏や中央公論社の名編集者・滝田樗陰氏を取り上げて紹介している。また、秋田出身の女流小説家・矢田津世子さんや山田順子さんにも触れられている。和田芳恵さんの甥だけに、血筋か文章が生き生きとし手慣れた感じを受けた。僕もある時、角館にある「新潮社記念文学館」を訪れ、あの懐かしい椎名其二さんや石川達三さんを紹介するパネルを前にし、しばし立ち止まり、ご冥福を祈ったものだ。
田村さんは仕事もできたが、遊びも仲間を募り、率先して遊んだ。将棋、麻雀、競馬、競輪などに熱中した。毎日のように麻雀をしたが、終電車がなくなると、田村さん、佐藤徹郎さん、僕の3人はタクシーで帰宅した。後には雀荘『樹林』の三郎さんの運転する車で、多摩センター(田村宅)→八王子西武北野台(加登屋宅)→西八王子(佐藤宅)の順で下ろしてもらい、御前様まで遊んだものだ。そして田村さんの段取りで、夏には新潟競馬、福島競馬に、冬は小田原競輪や伊東競輪に出掛けるなど、約10名近い遊び仲間は、徹夜で各種ゲームを楽しんだ。囲碁は佐藤徹郎さんと三枝篤文さんが、あまりにも強くて勝負にならず、田村さんも全員で遊べるゲームを選んだのだろう。遊びの面でも本当に名幹事ぶりが際立っていた。
・その佐藤徹郎さんが、11月の雨がそぼ降る日、わが社を訪ねてくれた。藤木君や臼井君のほかに4名の総勢7名で、中華料理店で昼食を摂ったのだが、その席で徹郎さんの話を聞くことができた。徹郎さんは、ダイヤモンド社の創立80周年記念事業で、『日本の伝統工芸品産業全集』(1991年)という後世に残る、貴重な豪華本を編集担当している。その時、編集や販売の戦略で手伝ってくれたのが田村紀男さんだったという。そのことを懐かしそうに話してくれた。

佐藤徹郎さんと僕
・徹郎さんは農業に対する造詣が深く、第一次産業の衰退に早くから警鐘を鳴らしていた。ダイヤモンド社時代も、「経済誌の専門出版社である弊社が、どうして農業本など出さなければいけないんだ」といった営業からの逆風もなんのその、剛腕とも言えるような力づくで出版したものだった。実際、販売実績が良かったこともあり、営業は沈黙を余儀なくされたのである。
清流出版からも何冊か、農業関連本を出させて頂いた。都合3冊あり、佐藤藤三郎さんの著になる『やまびこ学校ものがたり あの頃こんな教育があった』、星寛治さん著『耕す教育の時代 大地と心を耕す人びと』、山下惣一さん著『農から見た日本 ある農民作家の遺書』である。


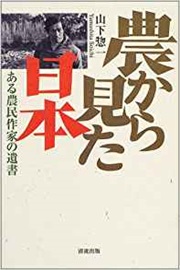
・徹郎さんが伝統工芸の豪華本を編集していた頃の僕はといえば、1991年にダイヤモンド社を去り、清流出版の立ち上げに、苦心惨憺していた時期である。出版業界に殴り込んで、旋風を巻き起こしたい、という熱い気持ちを胸に秘めていた。その頃のことが懐かしく思い出される。お蔭で二度、脳出血になり、一命を落とすかと思ったが、右半身不随と言語障害で済んだ。思い通りにはいかず、忸怩たる思いが去来するが、すでに清流出版も四半世紀という歴史を刻んだことになる。僕自身、信じられない思いである。願わくば、志を胸に刻んだ僕の後継者たちが、輝かしい未来を築いていって欲しい、そう心から願ってやまない。
